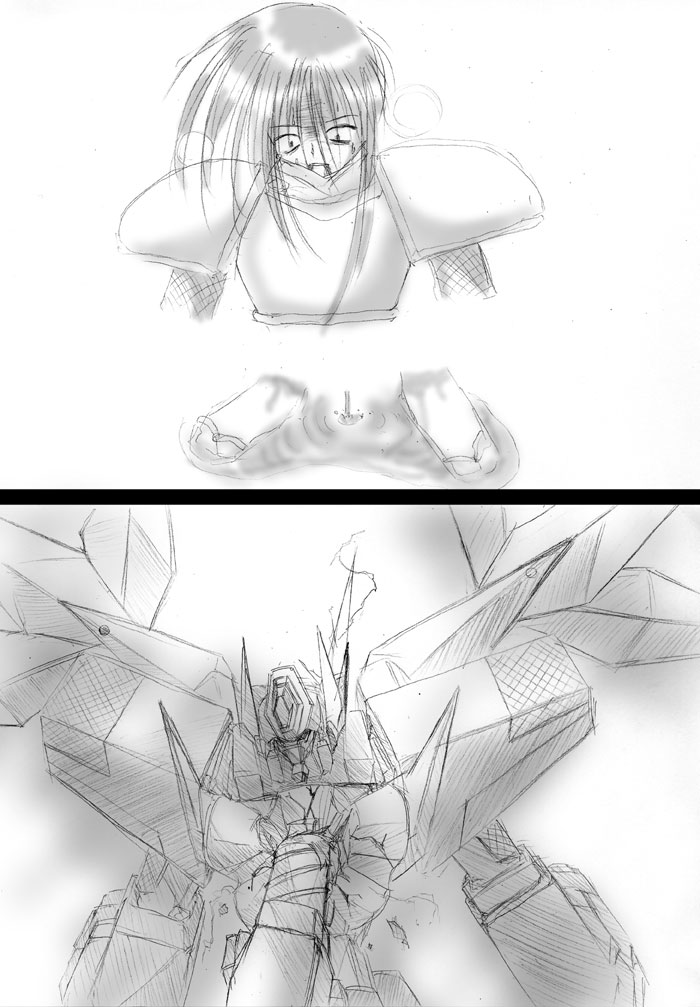|
「風雅……陽平」 陽平と釧、両者の視線が真正面からぶつかり合う。 そうだ。釧ほどの男がなにもせず、ただ捕らえられるなどあるはずがない。 その強靭な精神力は、獣王の攻撃が腐獣王を追い詰めていく度に、腐獣王の精神を蝕むように支配していったのだ。 今や、腐獣王に釧を縛る力はない。最凶であるその力さえも、最早釧の力の一部にすぎない。 「忍邪兵だろうと…、風雅の忍びであろうとも……我が心を侵すことなどできん」 まるでこの仮面がその証であるとばかりに、沈む陽を浴びて神々しい、しかし無機質な輝きを放つ。 「なら話は早ぇ。光海を……返せ」 一瞬、トーンの変わった陽平の言葉に、釧は頭上の存在を思い出す。 なるほど。今日の陽平の気迫はそういうことだったのか。 「力づくで……取り戻せ」 大切なものならば、失いたくないのならば力を示せ。それが風雅の血をひく者の運命なのだから。 「ちっ…、なら仕方ねぇ! てぇめぇの言い出したことだ。後悔すンじゃねぇぞ!!」 咆哮と共に身構える陽平に、釧は腐獣王の身体へと全身の神経を伸ばしていく。 いつもとは違う一体感に顔をしかめながらも、馴染み始めた力に拳を握り締める。 「翔けろ…カオスケラードストライカー」 鋼の翼を広げ、混沌の腐獣王が疾走する。 「迎え撃て、クロスフウガっ!!」 こちらも翼を広げ、紅い残像の尾を引きながら大地を蹴る。 左の獣爪同士が交差する。右の一角と刀が火花を散らす。互いに技と技との応酬が交わされる中、黄金の角が獣王の肩を削り落とし、斬影刀が腐王のパーツを切り裂いていく。 一撃の破壊力でスパイラルホーンが勝るのはわかっている。それだけに陽平は可能な限り手数を増やしていくが、まるでその全てが見抜かれているかのように容易く捌かれていく。 切っ先が空を切る度に陽平の中の焦りが大きくなっていく。 (なんで…) 無数の小技に織り込むように、超至近距離からの霞斬りを放つが、スパイラルホーンの生み出す渦の流れが、斬影刀を僅かに逸らしていく。 釧にしてみれば、回避するのにその僅かなズレは、見切るのに充分すぎる間合いとなるわけだ。 (なんで当たらないっ!!) 陽平と釧の実力に差があることは、陽平自身が一番良くわかっている。クロスフウガとカオスケラードストライカーの性能に差があることもわかっている。だが、いくらなんでもこれだけ当たらないのはどこか普通じゃない。まるでこちらの次の手を見抜かれているような不気味な感覚に、陽平は愕然とした。 「まさか…!」 陽平の脳裏に浮かぶ一つの答えは、ボロボロな心と身体に最悪の現実を突き付けてくる。 「俺と同じ鬼眼?」 陽平の瞳は、見た動きをそっくりそのままコピーする〝複写〟の鬼眼。だが、複写以外の鬼眼もまた、陽平の中には存在した。 見たものを全て記憶して、莫大な情報として蓄積する〝記憶〟の鬼眼。それは、相手の動きや癖、戦闘パターンを確実に記憶してしまうために、一度見た技は二度と通じなくなるという悪魔のような能力だった。 だが、その能力はあまりに不安定で、陽平の意思に関わりなく発動する上に、体力を根こそぎ持っていかれるため、陽平自身は裏技的な感覚で覚えていたのだが、今の釧は、どこか〝記憶〟の鬼眼に通じるものがある。 「鬼眼など関係ない。キサマの動きが至極読みやすいだけのこと…」 よもやこの土壇場にきて、釧の鬼眼が進化を遂げるとは思ってもみなかった。 だが、なにか妙な感じがする。これは新たな力が目覚めたというよりも、眠っていた力が開放されていくかのような印象を受ける。 どうやら鬼眼にも、まだまだ知らねばならない秘密が多々あるようだ。 突き出す刀にカウンターで膝を叩き込み、裏拳のように払うスパイラルホーンがクロスフウガを大地に叩き付ける。 手をついた反動で横へ飛び退き、追撃をかわすと同時に裂岩を切り離していく。 「いけッ!!」 次々に飛来する巨大な刃を払い除け、釧は険しい瞳を見せる。 スパイラルホーンが右手を完全に覆うために絶岩や右のシュートブラスターが使えないのを逆手に取る気か、近接から中距離へと距離を置くつもりらしいが、そうはいかない。 螺旋金剛角の威力を真正面に放つと、バリケードのように襲いかかる裂岩をいとも容易く砕いていく。 「野郎っ! いつもより随分と派手じゃねぇかよ!!」 光の槍を避け、後退しながら放つクロスショットの威力に舌打ちしながら、咄嗟にシュートブラスターの引き金を引き続ける。 「どこまで逃げるつもりだっ! 風雅陽平っ!!」 アンカーのように飛ぶ獣爪がクロスフウガの顎を捉え、陽平は大きくのけ反るように吹っ飛ばされていく。 (逃げ…る?) 釧の言葉が突き刺さる。 そうだ。逃げていては光海を救うことなど出来ようはずがない。 光海のために本気で怒った友人の言葉から逃げ、強い敵の手から逃げ、今は釧の猛攻から……いや、自身に向けられた揺るぎない意思と、恐ろしい現実から逃げている。 いったい、これ以上なにから逃げようと言うのだろうか。 (光海…、お前は俺を追いかけて──) 振りおろされるスパイラルホーンを両手で受け止め、背中のバーニアを吹かせて押し返す。 「……るか」 陽平の口から漏れる言葉に、釧は訝しげな視線を向ける。 「俺だけが逃げてたまるかぁぁぁっ!!」 咆哮と共に陽平の巫力が爆発する。 鋼の翼が風を呼び、獣王を中心に竜巻を生み出していく。 地を蹴ったクロスフウガの姿がかき消え、次の瞬間にはカオスケラードストライカーを力任せに殴り飛ばしていた。 「な──」 釧が殴られたと認識した瞬間、凄まじい圧力が胸に押し付けられ、捌く暇も与えられずに弾き飛ばされた。 「風遁を纏った……掌打だと!?」 打たれたと同時に触れた部分が鋭利な風の刃に切り裂かれていく。 咄嗟に防御するものの、荒れ狂う突風は容赦なくカオスケラードストライカーに襲いかかっていく。 (確かに凄まじい…) 「だがっ!!」 力加減もペース配分もあったものではない。このまま続ければいずれ体力の限界で力尽きることになる。 今の陽平は、ただ一心にこの状況の出口を探して暴走しているだけにすぎない。 「それもまた〝逃げ〟であると何故気付かない! 風雅陽平っ!!」 金色の渦が突風を裂き、クロスフウガの纏う竜巻と、カオスケラードストライカーの金色の渦がぶつかり合う。 「逃げるかよ!! 逃げてたまるかよっ!! 俺は逃げねぇ、てぇめぇからも、光海からも逃げてやンねぇぞぉっ!!!」 爆発したかのように広がる竜巻に、無数の裂岩を同時に切り離す。 「食らえっ!!」 風に乗る裂岩を巧みに操り、カオスケラードストライカー目掛けて次々と飛ばしていく。 打ち落とされるのは予測の範疇だ。真に狙うは、連続攻撃を捌き続けるという固定動作を誘うこと。 その間に裂岩を組み替え、風遁の印を組む。十字手裏剣に風の刃を持たせた一撃ならば、さしもの釧も受け止めはしないはず。そもそも、そんな危険を冒さずともカオスケラードストライカーのスピードならば容易くかわせるはずだ。 ならばその一瞬を狙い、渾身の疾風斬りで頭部を狙えば、少なからずカオスケラードストライカーの動きを封じることはできるはず。 釧の読み通りこの風遁によるスピード強化も、そう長くは続かない。 (今だっ!!) 身体の回転を利用して裂岩十字を投げ、同時に霞斬りで加速する。 案の定、カオスケラードストライカーは風遁裂岩十字を受け止めはせず、身を低くしてやり過ごすと、いつもの倍近い速度にまで達したクロスフウガを迎え撃つ。 だが、そんな体勢からまともな技が繰り出せるはずもない。それこそ、それが可能なのは陽平の疾風斬りくらいなもの。 「この間合い! たとえてぇめぇが神だろうと外しはしねぇ!!」 「それが甘いと言っている!!」 背面の大型ブースターを全開に、カオスケラードストライカーが飛び出していく。 左手で絶刀を引き抜き、陽平の疾風斬りと同じタイミングで刃が交差する。 「な──っ!?」 「キサマごときが編み出せる技が、風雅に存在しないと思っていたのか…!」 どれほど速度に変化をつけても、どれだけ有り得ない角度から攻撃を繰り出そうとも、絶刀は必ず間に割って入ってくる。 (くそっ、超えられねぇ!?) 「陽平、冷静になれ! 同じことを繰り返したところでヤツには通じない!」 「わかってる! けど──」 陽平の中に生まれたほんの僅かな隙を、釧が見逃すはずがない。 カオスケラードストライカーの一閃が斬影刀を弾き飛ばし、鞭のようにしなった蹴りがクロスフウガを大地へと叩き落とす。 派手に土煙を巻き上げながら落下したクロスフウガは、徐に膝をつくと、ゆっくりと舞い降りるカオスケラードストライカーを油断なく睨み付ける。 「確かにキサマは強い。鬼眼などなくとも戦う度に強くなる…」 釧の唐突な発言に、陽平はわけがわからないとばかりに訝しげな視線を向ける。 「だが…、覚悟が足りない。今のキサマが相手ならば、たとえ風雅を超えた技を繰り出そうとも、キサマに勝ち目はない」 絶刀の切っ先がクロスフウガの眉間を捉え、その異常なまでの気迫が圧力となって陽平に叩き付けられる。 「…万に一つもな」 「ぅるせぇよ…。覚悟なんか二の次だ。俺は……てぇめぇをブチのめして光海を取り返す! それだけだ!!」 再び爆発する巫力に、珍しく釧が驚きの表情を浮かべる。 それもそのはず。陽平は先ほどがら無駄とも思える量の巫力を開放しているというのに、いったいどこにこれだけの余力があるというのだろうか。 この巫力の総量は、たとえ巫女であっても考えられない。それこそ、カオスケラードストライカーのように外部から吸収を続けていなければ有り得ないことだ。 巫力の流れは確かに存在する。だが、その根源がなんであるかがわからない。 風雅がなにか特殊な秘術でも生み出したのか、それとも…。 「これは…!?」 周囲から巫力を集めているというのはどうやら間違いではなかったらしい。だが、その流れの根源が、よもや自身であったなどといったい誰が考えただろうか。 (カオスケラードストライカーの…俺の巫力を取り込んでいるのか!?) クロスフウガにそのような能力があるというのは聞いたことがない。陽平にそんな力があるとも思えない。では、いったいなにがこのような事態を招いたのか。 (……ぃ) 「なに?」 頭の中から響くような声に、頭痛にも似た感覚に襲われる。 (よ…う…へ…い…) これは声というよりも祈り。誰かが陽平を傷つけることを拒み、釧の思考に割り込んできている。 「これは…森王の巫女か!?」 本来、腐獣王の力の供給源と化してしまった巫女が、このような形で抵抗できるとは思えない。とくに光海は巫女としての修練も積んでいない未熟な身。 では、この現象はただひとえに陽平を想う光海の心が生み出したとでもいうのだろうか。 「いちいち癪に障る…。ならば祈りなどなんの力にもならないことを証明してやるっ!!」 釧の咆哮と共に金色の光が溢れ出す。 怒りや憎しみもまた強靭な心の形。それに呼応するように、カオスケラードストライカーもまた莫大な巫力を開放する。 巫力と巫力のぶつかり合いとは、心と心のぶつかり合い。両者の強き意思のもと、互いの忍巨兵までもが空気を震わせるほどの咆哮をあげる。 「クロスフウガ、釧の野郎は無視しろ! 俺たちの目的は光海だけだ!!」 「応ッ!!」 風遁の印を組み、生み出した風の塊を右手で包み込むように握り締める。隙間から溢れ出す風が頬を叩き、髪を乱し、陽平の全身を吹き飛ばさんと荒れ狂う。 「宿れ、風…遁っ!!」 全身に行き渡る力を右腕だけに集中させ、巻き上がる風をただひとえに研ぎ澄ませていく。刃よりも…、カマイタチよりも薄く、鋭く。 「我は…風也っ!!」 裂帛の気合いと共に、獣王が地を蹴って駆け出した。 霞斬りを凌駕する速度で間合いを詰める獣王に、釧もまた、勝負とばかりに腰溜めにしたスパイラルホーンを突き出していく。 「一閃…、螺旋金剛角っ!!」 背中の大型ブースターが火を吹く。僅かな溜めから一瞬で不可視の速度にまで達すると、クロスフウガ同様に一迅の風となって飛び出していく。 風と風。小さな微風はより大きな風に呑まれることとなる。 ならば互いにすることはただ一つ。相手よりも早く、強く、鋭く己を研ぎ澄ませ。 「う……あああああああっ!!!」 陽平の咆哮が裂帛の気合いとなって駆け抜ける。 「はぁああああああっ!!!」 釧の咆哮もまた、鋭利な刃物のように空を裂き、地上を駆ける風となる。 両者の間にピン、と張り巡らされた糸が焼き切れた瞬間、互いに必殺の一撃を繰り出した。 「貫けっ!! 風牙ぁ!!!」 「突き崩せっ!! 閃角っ!!!」 互いの技が放たれた瞬間、その僅かな差が二人の目にははっきりと映し出されていた。 閃光の一角と疾風の手刀・風牙。互角と思われたその切っ先。刹那の瞬間にせよ、速さを制したのは陽平であった。 僅かに触れた指先がスパイラルホーンの切っ先を通り越し、肘を越え、腕を越え、眉間に触れ── 風雅の里から遠く離れた地。山奥の道なき道を行く柊の耳に届いたのは、小さな風の吹き抜ける音であった。 ふと誰かに呼ばれたような気がして振り返ってみれば、目の前を一枚の葉が舞い散る瞬間であった。 「アニキ…?」 葉が散るような季節ではないはずだ。それほど強い風が吹いたわけでもないはず。 葉がひとりでに落ちただけ。そう考えるのは簡単だが、どうにも気になって仕方がない。 そういえば、葉を枝に繋げている部分を葉柄と言ったはず。葉が落ちたということは、その葉柄が折れたのだろう。 (まさか…) ようへいがおれた── 「アニキっ!?」 遠く離れた地に残った少年の姿が霞んで見える。 いや、まさかそんなはずはない。彼に限ってそんなことがあるはずがない。 彼と共に在るのは最強の忍巨兵・獣王だ。それになにより、勇者忍者である彼が、主を残して逝ってしまうなどありえない。 「……アニキ、必ず戻ってくるかンね!」 すぐにでも帰りたい気持ちを押し殺し、踵を返して駆け出していく。 今の柊にできることは、一刻も早く忍巨兵を目覚めさせて里に戻ることだ。 そもそも、歩くなど性に合わない。目的地まで走り続けてやる。 風魔の少年は今、地を駆ける風となった。 同時刻──。 兄と別れて、一人目的地へと駆ける少女の姿が在った。 一心不乱に走り続けるその姿を少女と呼ぶのは、あまりに強き意思を秘めている。 そうだ。彼女──風魔楓は少女である前に一人のクノイチだった。 彼女に与えられた使命は二つ。〝未だ眠り続ける忍巨兵を目覚めさせること〟と〝必ず帰ること〟。 使命を果たすためには、振り返る時間さえ惜しんで走り続けるしかない。たとえ、己が仕える頭に危険が迫ったとしても、だ。 (振り返ってはだめ! 今振り返ってしまったら……きっと走れなくなってしまう) 虫の知らせというのだろうか。今この瞬間に、陽平の身になにか良からぬことが起きているのは間違いない。だが、決して歩みを止めることはできない。何故なら、彼が待ち望んでいるのは使命を果たした楓であって、成すべきことを放棄して、感情のままに舞い戻る楓ではないのだから。 少なくとも、楓本人がそう考えている以上、ここで引き返すわけにはいかない。 「先輩…!」 不意に、背中から通り抜けていく風が、獅子の咆哮を運んできた気がした。 それは、決して聞き違えることのない彼の悲鳴に他ならない。 徐々に歩み足になる自分を必死に奮い立たせ、振り返りたくなる気持ちを無理矢理押し込める。心臓は早鐘のように鼓動を打ち、次から次へと湧き上がる感情に、楓自身が一番戸惑っていた。 キツく噛み締めた唇の端から、一筋の赤い滴がこぼれ落ちていく。 果たしてこぼれ落ちるのは一握の希望か、それとも…。 ようやく落ち着きを見せた自分に安堵の息を漏らすと、楓は手首に巻いていたゴムバンドで髪を束ねていく。 これは彼女なりの気持ちの切替えだ。いつもの自分とは違う。普段の自分を脱ぎ捨て、ここからはクノイチとしての自分になる、と。 「必ず戻ります…!」 伊達眼鏡を外し、小さく呼吸を整えると、楓は己が使命を果たさんがために駆け出した。 風雅の里の最奥部。蒼天と呼ばれる忍巨兵を製造している工場では、突き付けられたあまりの残酷な現実に、誰一人として言葉を発することができなかった。 いや、それが現実であるかを確かめることさえ躊われた。 中には力なく崩れ落ちる者も少なくはなく、風雅当主・琥珀もまたその一人であった。 「どうして…、どうしてなのですか!?」 艶やかな黒髪を振り乱して頭を振り続ける琥珀に、そっと肩を抱き締めるように日向が寄り添う。 希望が砕け散る瞬間。それはあまりに凄惨で、誰一人としてその事実を直視できるものはいなかった。 そんな中、一人工場を駆け出していく者の姿が在った。 幼すぎる心が求めるのは、ただ優しく強い、兄のような少年の姿。 風雅陽平の主にして、リードの姫である少女──翡翠は、息を切らせながらもただひたすらに空を求めて走り続ける。 「ようへい…」 名を呼べば、いつも笑顔を返した少年がいた。 「ようへいっ…!」 名を叫べばいつも助けてくれた少年がいた。 その少年が今、翡翠を置いていなくなろうとしている。翡翠にはそのことが痛いほど伝わっていた。 胸が苦しいのは、走り続けているからなんかじゃない。不安が、絶望が心を押し潰そうとしている。 助けて── 心が悲鳴をあげている。 「助けて…!!」 それは誰でもない。ただ一人の少年に向けられた言葉だった。 獣王の手刀は確かに早かった。 風を越えた突きは、閃角の一撃を越えてカオスケラードストライカーの眉間を捉えたはずだった。だが…
|