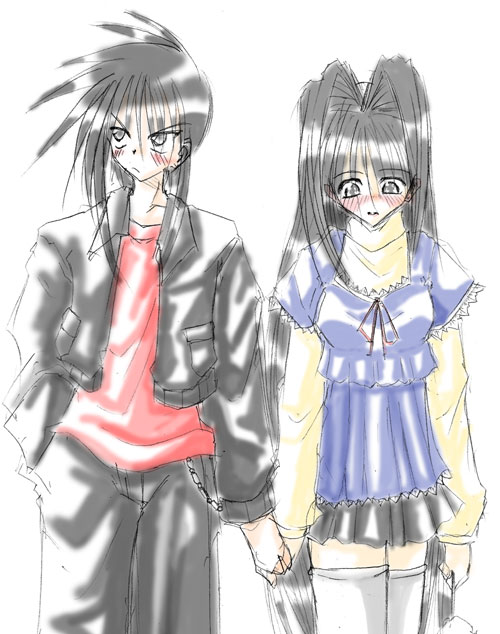|
巨腕の猛襲を退けて数日、勇者忍軍の面々は、それぞれ当たり前の生活を送っていた。
不思議なことに、あれから一度もガーナ・オーダは現れていない。むしろ、もう現れないでいてほしいと思うのは、決して自分だけではないはずだ。
せめて……、せめて今日一日だけは、そのことを忘れていたい。それが桔梗光海の願いだった。
先日、部活を終えて帰宅しようとした光海の下に、幼馴染みのあいつが現れた。
いつもぶっきらぼうなくせに、その日はなぜか照れ隠しをしながら校門で待っていてくれたらしい。
どういう風の吹き回しかと尋ねれば、彼はとんでもない言葉を言ってのけた。
一瞬、聞き間違いかと思い、尋ね返す光海に、風雅陽平はやはり照れ隠しでそっぽを向きながらこう告げた。
「だぁかぁら。……明日、俺とデートしようぜ」
そのときね陽平は、顔から火が出そうなくらい赤面していたに違いない。
だが、断る理由などない。むしろ、火急の用があっても忘れることにした。
長い黒髪を櫛で梳し、わからない程度に薄い化粧をする。
まだまだ若いのだ。化粧などよりも素材で勝負。とは、母の言葉だ。
まだ着たことのなかった新しい服に袖を通し、いつもとは違う自分を印象付ける。
まぁ、あの唐変木のことだ。お世辞のひとつも言えないだろうけど、きっと態度で示してくれるに違いない。
それに、今日のデートではあいつに伝えたい言葉がある。それが成功しないことには、話にならない。
強い決意を胸に秘め、小さくガッツポーズすることで自分の気持ちを高めていく。
装備も、気力も十分に整った。これで戦闘準備は万全。
「頑張れ私。今日こそヨーヘーに『好き』って言うんだから」
時計の針が約束の一時間前を指し、今までの人生中、最大の作戦が開始される。
カレンダーの今日の日付には、赤いペンで丸が印してあり、そこには〝ヨーヘーとデート〟の他に、〝告白〟と小さく書き込まれていた。
『最高の一日』
正直驚いた。
約束の三十分前に待ち合わせ場所である時非駅に到着した光海は、既に到着していたらしい少年の姿に驚きを隠せなかった。
しかも、どこかイライラした様子が見え隠れしているということは、かれこれ一時間近くはああしているということだろう。
自分から誘ったから待たせちゃ悪いと思って、時間より早くに来るなどといった殊勝な気持ちがあったとは露知らず、光海は幼馴染みの新たな一面に頬を弛ませた。
とにかく、事情はどうあれ待たせてしまったのは自分なのだ。ここは急ぐことにしようと、小走りに陽平の下へと駆け寄っていく。
「ヨーヘー!」
声をかけるより早くこちらに気付いたらしい少年に手を振り、いつもの距離で立ち止まる。
「ごめん、私遅刻しちゃったね」
約束の時間にはまだ三十分はあるのだが、そんなこと、待っていてくれた人には関係ない。
だが、そこで返された言葉に、光海は思わず目を丸くした。
「いや、俺が早く来過ぎただけだからな。気にすンなよ」
そう言って笑いかける陽平は、あまりにいつもの彼とかけ離れていた。
出鼻を挫かれ、いくらか調子が狂った気がするが、こんな陽平はめったにないので存分に堪能することにしよう。
「なぁ、光海」
「なに?」
急に真面目な顔をするものだから何事かと思ったが、ここでも陽平は想像の斜め上を行った。
「に、似合ってるぜ」
「ぇ……?」
「服だよ」
改めて上から下までを見直し、頬を掻きながら照れ臭そうにそう告げられれば、さすがに光海も気恥ずかしくなってきた。
いったいどうしたというのだろうか。まさか、今日が人類最期の日というわけでもあるまい。
だが、それにしては陽平が優し過ぎる気がする。
少し不安になって周囲を伺うが、監視されているような気配はない。もっとも、陽平たちのように視線などに対して敏感というわけでもないので、どこまで確かかはわからないが。
「どうした。なンかあったか?」
きょろきょろとしていたために、普通に心配されてしまったようだ。
しかし、そんな姿はいつもの陽平と変わらず、なんだか安心してしまう。
「そういえば、今日はどこに行くの?」
誘ってもらったことにばかり浮かれていたが、肝心なことを聞いていなかった。
ひょっとしたらこんな格好では動き辛い場所ということだって考えられる。
「歩こうぜ」
「あ、ちょっと待って」
そう言って急に歩き出され、思わず陽平の腕に手を伸ばしてしまう。
さすがにこれは嫌がられるかと思い、手を離して「ごめん」と謝る。
陽平が優しいからか、少し有頂天になっていたのかもしれない。
恋人同士でもないのに腕を組むなどと、少しばかり空気を読めていなかった。
「なにしてンだよ」
「え?」
「ほら、行くぜ」
差し出された陽平の手に、光海はやはり我が目を疑った。
見上げる顔は、やはり恥ずかしいのか、どこかぶっきらぼうなままで、それでも光海が握り返すことを待っている。
「いいの?」
おそるおそる尋ねてみたが、陽平は黙ったままもう一度手を差し出すので精一杯だったらしく、顔を背けて光海の行動を待っている。
「じゃあ……」
早鐘のように打つ心臓を落ち着かせながら、そっと陽平の手に自分の手を重ねる。
触れた瞬間は冷たいと思った掌は、ただ重ね合うだけで汗ばむほどに熱くなった。
二人の体温が混じり合ったと思うだけで、頬が朱を散らせたように染まっていくのがわかる。
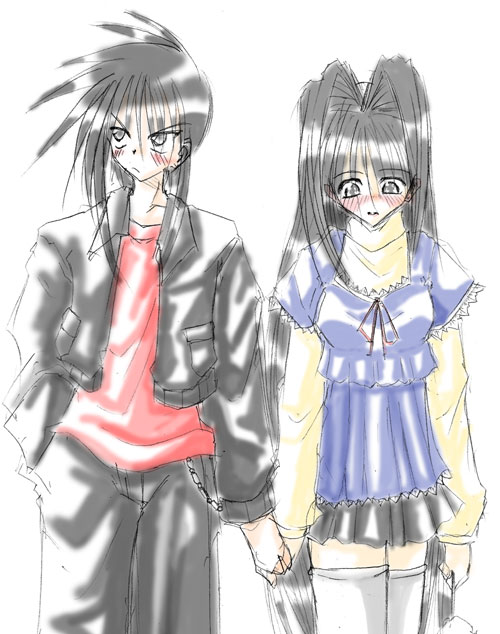
「い、行くか」
「……うん」
二人三脚のように、息を揃えて二人同時に足を出す。
今まで幾度となく夢に見た、陽平との恋人同士のような時間が始まった。
最初は見られると思うだけで恥ずかしく、お互いに会話も交わせないまま歩き続けたが、それは長くは続かなかった。
陽平の振る話にいつものような軽口を返しているだけで、いつしか自然に互いの手を握り、終いには腕を組むほどの進展を見せた。
ショーウィンドゥの巨大なぬいぐるみを見て、かわいいだ、かわいくないだと言い合い、帽子売り場では七変化も披露した。
何をするのも楽しくて、ただ陽平にだけ見てもらいたくて。
腕を引き、困った顔を見せる陽平を引っ張り回し、クレープをねだってみたりもした。
その度に陽平は「しょうがねぇな」と呟きながら光海に従い、いつもは見せないような一面をさらけ出してくれる。
ベンチに座り、少し肌寒い風に髪を押さえ、クレープを頼む陽平の背中をじっと見つめる。
ずっと、この背中を見て育ってきた。初めて好きと思ったその日から、今の今まで目を反らすことなく。
クレープを受け取り、器用なことに、同時に四つも持って駆け寄る陽平に、光海はさすがと苦笑を浮かべる。
差し出された右手から二つのクレープを受け取り、隣りに腰を落ち着ける陽平を目で追いかける。
「どうした? たしか、バナナクリームと抹茶で良かったよな」
渡したものを間違えたと思ったのか、自分の手にしたクレープとこちらのクレープを交互に見比べている。
「ううん、違うの。ただ、ちょっとサービス良過ぎかなって思って……」
確かに二種類を食べてみたいとは言ったが、まさか両方とも買ってこられるとは思っていなかった。
食べ切れるかという心配よりも、陽平が無理していないかと、そちらばかりに気がいってしまう。
だが、そんな不安を察してか、「ばぁか」と悪態つきながら肘で頭を小突かれ、光海は目を白黒させる。
「そんなくだらねぇ遠慮すンじゃねぇよ。たまにゃそんな日があったって、バチなんか当たりゃしねぇよ」
自分でも珍しいことは自覚しているのか、そんなフォローを入れてくれる幼馴染みに自然と頬が弛むのを感じた。
一口囓ったクレープはとても甘くて、それだけで幸せな気持ちになれる気がした。
「うん。美味しい」
「だな。それじゃ、俺も……って、なにやってンだよ」
見れば少女が覗き込むようにして、陽平のクレープに囓り付いているではないか。
「翡翠ちゃん」
「ん。おいしい♪」
そんな、陽平の手から食べるなんて羨ましい……ではなくて、この少女の接近に、陽平が気付かないはずがない。
乗り出したベンチからぴょん、と飛び降りると、「ごちそうさま」と丁寧にお辞儀する。
彼女が動く度、二つに縛った髪が可愛らしく揺れる。
残念だが、自分にはない魅力だと痛感させられる。
「なにやってンだよ、こんなとこで」
「ともだちと、あそんでる」
なるほど。向こうに見える少年少女が翡翠の友達というわけか。
学校などでも上手くやれているらしく、その姿はどこか微笑ましかった。
そういえば、陽平は彼女についていなくても大丈夫なのだろうか。最近動きを見せないとはいえ、ガーナ・オーダに狙われている彼女を放っておくなど愚の骨頂。
しかし、陽平はいつものように翡翠を嗜めると、手にしたクレープを二つとも手渡して友達の下へと返している。
「いいの?」
こちらの言わんとしていることはわかっているらしく、陽平は親指に残ったクリームをペロリと舐めて翡翠に手を振りながら、「大丈夫だよ」と答えた。
「癪な話だけどな。今日は親父がついてっから、俺が一緒よか安全だぜ」
そう語る陽平は、確かに釈然としない表情をしている。
そういえば、ついこの間は過去にタイムスリップしていたと聞いたが、どうにも帰ってきてからというもの陽平の様子がおかしい気がする。
どこがおかしいと明確に答えることはできないが、何か雰囲気が違う。
少なくとも、以前よりもみんなのことが見えているし、少し大人びた顔をするようになった。
過去で何かあったのだろうか、とも思ったが、明智光秀に会ったらしいこと以外は、語ってはくれなかった。
「なんだよ。人の顔ジロジロ見て」
「え! あ、く、クレープあげちゃって良かったのかなって」
慌てて取り繕ったが果たして上手くいったかどうか。
「まぁ、たかりに来たっぽかったしな。それに、いくら姫とはいえ、デートしてンのにコブ付きはまじぃだろ」
自分で言っておきながら照れ笑いを浮かべる陽平に、しょうがないと手にしたクレープを差し出す。
こちらの抹茶にはまだ口をつけていない。陽平も気兼ねなく口にできるはずだ。と思ったのだが、陽平は光海の手を取ると、もう一方のバナナクリームを一囓り。もぐもぐと満足そうに頬張っている。
「おー。普通に美味ェや。定番ってのは、誰が食っても美味いから定番なんだろぉな」
そんな当たり前のように語られても、今の光海には言葉を返すだけの思考が存在しなかった。
陽平が光海の手からものを食べるのは、これが初めてのこと。いわゆる「あ~ん」という行為に相当する……と思うのだが、できることなら初めての「あ~ん」は手料理でやってほしかった。
実は以前、弓矢で「あ~ん」を実行しているのだが、そんなことは当の昔に忘れているのでノーカウントとしたい。
とにかく。さすがに今の行動は、焦るなという方に無理がある。
息苦しくなるほど早く打つ鼓動を必死に堪え、もう片方のクレープと見比べる。
囓った跡のない抹茶クレープと、光海が囓った跡が陽平に上書きされたバナナクリームクレープ。
それに気付いた瞬間、またしても一瞬で頬が熱くなる。
(これ……間接キス)
キスというものはなかなかに厄介で、一度意識してしまうと相手の唇ばかりに目がいってしまうようになる。
唇の僅かな動きや、話すときのクセなど、その一つ一つが心臓を大きく跳ね上げる。
「なんだよ。怒ってンのか?」
「そうじゃない……けど」
そうじゃない。むしろ嬉しさを我慢できなくて困っているくらいなのだ。
しかし、それを素直に語ることができずにそのまま押し黙るものだから、怒っていると勘違いされるのも仕方のないことだった。
「とにかく、怒ってないの。ただ、ちょっと驚いちゃって」
クレープだけではない。今日の陽平には、ずっと驚かされてばかりでいる。
そうだ。驚いてばかりで気付けないでいたが、これは何かが違う。上手く説明できないけど、陽平らしくない。
自分の知っている陽平は、自分にだけ優しいなんてことは絶対にない。忍者バカで、誰の心にだってずけずけと入り込んで、ぶっきらぼうで、翡翠を守ると息巻いていて……。
こんなの……らしくない。光海の好きになった〝ヨーヘー〟は、こんな陽平ではなかったはずだ。
誰にだって優しい中で陽平の一番になる。それが光海の願いだったはず。
「ねぇ、今日はどうしちゃったの?」
一つ一つ言葉を区切りながら尋ね、陽平の様子を伺うように上目遣いになる。
「なんか、ヘンだよ」
「楽しく……ねぇか?」
その聞き方はズルいと思う。自分にだけ優しい人とのひと時。楽しくないはずがない。嬉しくないはずがない。しかも、それが想い人なら尚更だ。
首を横に振る光海に、陽平は困ったように頭を掻くと、視線をうろうろと彷徨わせる。
「あ~……。なんつーか、言いたいことはわかるンだ。俺も、本当はなンか違うなって思ってたしさ」
それはつまり、自分の行動に疑問を持っていたということなのだろう。
「やっぱり、俺らしくねぇよな。わりィ、ここからはいつもの──」
そこまで口にした陽平が、慌てた様子で立ち上がる。
いったい何事かと顔を見上げれば、既にいつもの顔に戻った勇者忍者の風雅陽平がそこにいた。
「ヨーヘー?」
「光海、ここにいろ! あの野郎には聞きたいことも、言ってやりたいことだって山程あるンだ!」
「ちょっと待って。ヨーヘー!」
そう叫んだときには時遅く、もう陽平の姿はそこにはなかった。
風雅の一つ。縮地法の透牙を使ったのだろう。
小さく溜め息をつきながら、食べかけのバナナクリームクレープを食べ切ってしまうと、もう片方のクレープに視線を落とす。
いくら変だといっても、そんな急にいつもに戻られても困るというものだ。
これでは余韻に浸る間もない。それに……
「ここじゃ一人は寂しすぎるよ。ヨーヘー」
カップルたちが寄り添う公園に一人残された光海は、周囲の視線から逃れるように自らの肩を抱き締めるのだった。
あの刺すような視線の主を、今更間違えるはずもない。
まさかこんな身近にいたとは驚きだったが、灯台下暗しという言葉だってある。
逃がさない。相手の気配は既に捕まえている。この透牙ならば、追いつくまでに、そう時間は……
「見つけたッ!」

既に見慣れた細身の長身に、左半面を覆う銀の仮面。自分によく似たクセのある頭髪。そして、未だにこちらに向けられたままの射抜くような視線。
「釧ッ!」
壁や看板を蹴って建物の側面を登り、目的の人物を跳び越えて着地する。
この短時間で、しかもビルの屋上にまで駈け登って来たというのに、さして驚いた様子も見せずにこちらを振り返る。
以前のような剥き出しの敵意はない。どうやらここで戦うつもりはないらしく、片手をポケットに入れたまま自然体でこちらを睨み付ける。
「やはり、以前よりできるようになった。風雅陽平」
「そォいうてぇめぇこそ、会う度に空気が変わってやがるぜ」
舌打ちする陽平に、釧は変わらぬ表情で左手に持った刀を持ち上げる。
獣王の証と呼ばれた刀、炎鬣之獣牙。残念ながら、これを相手に生身で勝てる要素は皆無だ。
「獣帝、確かに恐るべき力だ。だが、真獣王と獣王の証は俺の手の内。キサマが上だとは思わないことだ」
警告。おそらくは、そういうことなのだろう。
確かに、獣帝となったあの日以来、陽平は一度として獣王式フウガクナイを抜いてはいない。
負けるはずがないと、獣帝という強大な力に安堵しきっていたことも事実だ。
どこで見ていたのか、そんな陽平に釘を刺しに来たということなのだろう。
(しかも、今日に限ってはデートだかンな)
釧にしてみれば、腑抜けた好敵手など見たくはないといったところか。
「忠告、感謝するぜ。だがな、獣帝が……マスタークロスフウガがいる限り、俺は絶対に負けない」
それは決して驕りなどではない。あの姿こそ、過去を守り、現代を戦い、そして未来を掴む最終形態なのだから。
負けるはずがない。いや、金輪際、負けてはいけないのだ。
「てぇめぇこそ人の心配なんかしてねぇで、いい加減翡翠に会ってやれよ! あいつがどんな気持ちでお前を待ってるか、考えたことあるかよ!」
「そのよく動く口、今ここで首ごと落としてやっても構わんぞ」
そういう釧こそ、明らかにいつもよりも饒舌になっているのは、おそらく好敵手と向かい合う高揚感を抑えられないためだろう。
「琥珀さんも、お前のことを心配してた。いつまでそうやって一人ぼっちでいる気なんだ」
陽平が過去から帰るまで、勇者忍軍の仲間たちを守ってくれたのは、この男だというのは聞いている。
ときには身を挺して、光海のことを救ってくれたとも聞いた。
「お前も俺なのか。俺がいるから来れないのか?」
陽平という人間にわだかまりを持つ者は、確かに存在する。
ある少年を巡り、陽平の行動を恨み続ける天城瑪瑙。
光海を我がものにせんと、……邪魔な陽平を付け狙う蓬莱光洋。
この二人はおそらく、陽平がいなければ忍軍の一員として共に戦ってくれる者たちだ。
もしも釧がそうだと言えば、いったい自分はどんな行動を選ぶのだろうか。
翡翠と釧のためと、潔く去るかと問われれば、それはノーだ。
どちらからともなく獣王式フウガクナイの柄に手をかけ、同じタイミング、同じ速度で同じ技を仕掛ける。
「「風雅流天之型ッ、輝針ッ!」」
二人の中央で、刃と巫力がぶつかり合う音が幾度となく鳴り響く。
「鈍っては、いないらしいな」
一際強い釧の振りに腕を弾かれる。
どうやら本当にここでやり合うつもりはないらしく、その隙に釧は獣王式フウガクナイを納めていた。
「お、おい。話を逸らす気かよ!」
「少なくとも、キサマと馴れ合うつもりはない」
くるりと踵を返す釧に手を伸ばすが、それは彼の背中から放たれる殺気によってはばかられた。
やはり生身でやり合っても勝ち目はない。先の輝針も、相打ちになったのは釧が合わせたからに違いない。
まだだ。まだ、釧との実力には大きな開きがある。
釧が現れたのは、おそらくそれを教えるためだったのだろう。
一度だけ振り返り、不敵というよりも邪悪な笑いを浮かべる釧。
今触れれば、まず間違いなく先の言葉通り首を落とされる。
「次に会うときまでに、せいぜい腕を磨くんだな。不敗を口にした以上、無様な死に様を晒したくはないだろう」
「ひとつだけ、聞かせてくれ」
その言葉に歩みを止めたということは、話を聞く気はあるのだろう。
過去から帰ってから、ずっと気になっていたことがあるのだ。
あの時代に出会った少女の姿は、今も変わらず瞼の裏に焼き付いている。
「琥珀さんと翡翠は……血縁者なのか」
姉妹とまでいかなくとも、従姉妹や遠縁の親戚という可能性もある。
そもそも、そうでもなければ、あの容姿の一致は説明がつかない。
背中を向けたままの釧から、彼の考えを読むことはできない。だが、答えないという行動こそが答えなんだと気付いた陽平は、「そうか」と呟くと、両手の拳を固く握り締める。
ようやくわかってきた気がする。本当に守らなければならないのが、誰なのかということを。
そして、その人物を守り抜くために、獣帝マスタークロスフウガが存在するのだと。
やはり、デートなどしている場合ではなかったのかもしれない。
だが、そこで陽平の思考がピタリと停止した。
今日、いったい何のために光海に喜ばれる陽平を演じてまでデートしていたのか。
それを思い出した瞬間、咄嗟とはいえ、陽平はとんでもない相手に相談を持ち掛けていた。
「あ、あのさ!」
「ひとつだけ、ではなかったのか」
目だけで振り返る釧が不機嫌そうな声を返す。
「わ、悪ィ。でもよ、お前だって俺の質問に答えてねぇじゃんか」
そうまで言うなら早く用件を言え。そんな無言の圧力が釧の全身から放たれる。
冷や汗をかきながら空笑いを浮かべると、陽平は言いにくそうに頭を掻いた。
「お前、女の子に贈り物とかしたことあるか?」
自分でもこの男を相手にしながら何を言っているのかわからなかったが、おそらく釧はそれ以上に何を問われたかわからなかったのだろう。
怒りからだろうか。彼の眉がピクリと震えたのは、決して見間違いではない。
「日頃の礼とか、そういうのも含めてさ。夏にできなかった誕生日を祝ってやりてぇんだよ」
最高の一日にすると約束したのに、あの日は誰にとっても最悪な一日にしてしまった。
むしろ、あの日を境に光海には心休まる日がなかったのではないだろうか。
そう考えた陽平は、友人の安藤貴仁に話を持ち掛けた。
正直、このときはまだ、相談相手を間違ったとは露ほども思っておらず、貴仁の言う〝光海の喜ぶ陽平〟を演じてのデートと相成ったわけだ。
しかし、結果は先の通り。光海にも、自分にも妙な違和感を残して作戦は失敗。しかも光海を残して釧を追いかけてきてしまったのだ。
あと、陽平に残された手段と言えば、気の利いた誕生日プレゼントくらいなものだ。
「頼む。正直、俺の知ってる男で、まともな答えが返ってきそうなのがお前くらいなんだ」
まったくもって、情けない話である。
貴仁は既に例外。雅夫に相談などできようはずもなく、柊はこういうものとは無縁の生活を送っていたはずだ。他にもクラスメイトなども考えられたが、どいつも真剣な答えが期待できない相手ばかり。
こんなこと、好敵手に相談するなど見当違いもいいところだが、今は藁にもすがりたい状況だ。
「……頼む」
追い討ちをかけるような陽平の願いに、やれやれと溜め息混じりの釧が、ようやく口を開くのだった。
寂しい。そう感じた瞬間、光海は知っている者の声を聞いた気がして、弾かれたように顔を上げた。
「桔梗さん、こんなところでどうしたんですか」
「天城……さん」
心配そうに光海を覗き込む小柄な少女は、頬にかかる髪をかきあげながら光海の顔色を伺っている。
どうやら俯いている姿を具合が悪いと勘違いしたらしい。
無理もない。両肩を抱き締め、一人ベンチで俯いている少女がいれば、光海だって具合が悪いのだと思う。
いつの間にかクレープは地面を濡らし、光海の手には何一つ残されてはいなかった。
いつの間にか手放してしまっていたのだろう。それはどこか、急に掌から大切なものがこぼれ落ちたような、そんな錯覚に囚われた。
「だんだん、寒くなってきたね」
答える代わりにそんな言葉で濁し、光海は陽の落ち始めた空を見上げた。
太陽が海の方に沈んでいくのを見ていると、不思議と陽平が帰ってくるような気がして来る。
「風雅……陽平ですか」
瑪瑙の問い掛けに、光海はただ、困ったように頷くしかできなかった。
瑪瑙がなにかしらの理由で陽平を避けているのは知っていたし、陽平もそのことについて触れないようにしていた。
自分の知らないところで何かがあったということが、気にならないはずがない。しかしそれでも、陽平たちが話してくれるまで待とうと、自分自身が決めているのだ。
(ヨーヘーのこと、信じてるから)
心の底から感じた気持ちに偽りがないことを確認すると、いつの間にか光海は笑顔に変わっていた。
「桔梗さん……?」
それはそうだ。さっきまで寂しがっていた人物が、なにもせずに突然笑顔になるなど聞いたことがない。
自分でも、おかしいとは思っているのだ。でも、待つのはわりと嫌いじゃないから。
「私には……わかりません。彼のような、優柔不断な人のどこがいいのか」
「違うよ」
首を横に振って瑪瑙の言葉を否定すると、頬が熱くなるのを感じた。
「優柔不断だから、ヨーヘーなの。それに、いざというときはカッコイイの。辛いとき、本当に欲しい言葉をくれて、無茶してでもみんなを守ろうとする。ヨーヘーって、そんなバカなんだよ」
思わず語ってしまったが、まさか瑪瑙を相手にノロケ話をすることになるとは思ってもみなかった。
だが、そんな光海に感じるものがあったのだろう。一度目を伏せると、次に開いたときには笑顔になっていた。
「桔梗さん、頑張ってください」
「ありがとう」
「それじゃ、私は行きます。彼、すぐに戻ってきますから」
そう言って踵を返す瑪瑙に頷くと、なんだか覚えのある気配が近付くのを感じた。
光海が振り返るのと、陽平が飛び降りてきたのは、ほぼ同時。
やけに疲れた顔をしているのは、巫力の使い過ぎだろう。おそらくは全力疾走の成れの果てだ。
「わ、悪ィ。待たせちまったな。って、ありゃ……天城か」
遠ざかる後ろ姿を見つけたらしく、首を傾げて光海に疑問を投げかける。
「ヨーヘーを待ってる間ね、話し相手になってくれてたの」
それを聞いても陽平は気にした素振りもなく、ただ「そっか」と呟くだけ。
やはり陽平は、瑪瑙のことを嫌っているわけではないらしい。
と、いうことは、瑪瑙が一方的に陽平を嫌い、陽平はそれを甘んじて受けていることになる。
(それは、ヨーヘーにやましいことがあるからなの?)
少し不安の表情を浮かべるが、陽平を前にそんな顔ばかりしているわけにはいかない。
「ところで。ヨーヘーは私を置いて、どこに行ってたのかな?」
少しおどけた感じに尋ねてみれば、陽平は困ったように視線を泳がせながら後頭部を掻く。
そういえば、陽平が手に持っているものはなんだろうか。
さっきまでは手ぶらだったはずだが、いつの間にこんなものを。それに、陽平が持つにはやけにラッピングが小綺麗すぎる。
光海が見ていることに気がついたか、陽平は「そうだ」とばかりにそれを差し出した。
「これ……私に?」
「前に約束しただろ。誕生日のプレゼントは改めてするってさ」
そういえば、風雅の里でのひとときに、そんな話をしていた気がする。
あの場しのぎの口約束というわけではないのはわかっていたが、まさか今の今までずっと覚えていたとも思っていなかった。
でも、陽平はずっとそうだった。
約束ならば、それがどんな小さな口約束でも、必死になって守ろうとする。
たとえそれが、どんなに古い約束でも。
先日の戦闘もそうだった。幼い頃交わした約束の通り、光海が助けを乞い、矢文で願ったとき、陽平は時間という壁すらも越えて助けに来てくれた。
「開けても、いい?」
「ああ」
飾りのリボンを解き、袋を破らないよう丁寧に開けていく。
長細い長方形の箱を二つに、そっと中身を取り出した光海は、手にしたそれに「あっ」と小さな声を漏らした。
それは滑らかな手触りの、真珠色をしたリボン。
「ヨーヘー……これ」
「悪ィ。俺には光海の喜ぶことも、光海の欲しい物もわからなかったンだ。付き合いだけは長ぇってのに、情けねぇ話だろ」
自嘲気味に笑う陽平に、光海はそんなことはないと首を左右に振る。
「俺、光海のこと知ろうともしてなかった。だから、貴仁の言葉も鵜呑みにして光海のことを不快にしちまった」
なるほど。陽平に妙なことを吹き込んだ犯人は、やはりあの少年か。
でも、陽平がそんな風に思ってくれただけで、光海にとっては大きな進展なのだ。
「だからさ、俺なりに光海に似合いそうな色を選んだつもりなんだ」
「うん。嬉しいよ、ヨーヘー」
陽平が真剣な顔をしながらリボンを選ぶ姿を想像してみると、なんだかおかしくて仕方がなかった。
「だ、だから……さ。それ……」
いったいなにを照れているのだろうか。顔を真っ赤にしながら、必死になって言葉を紡ごうとする陽平に、光海はきょとんとした面持ちで小さく首を傾げた。
「その……だから、だな。俺がつけてやるよ、そのリボン」
「えっ!」
一瞬、陽平の言葉に呆気に取られながらも、今度は光海が真っ赤になる番だった。
ひったくられるように手からリボンを取られると、肩を掴んで背を向けさせられる。
髪に触れられた瞬間、光海の胸が、ドキン! と跳ね上がる。
冷たい風にさらされた光海の髪を、陽平の手櫛が丁寧に梳していく。
痛くはない。それどころか気持ちいいとさえ感じる陽平の手に、光海は複雑な表情を浮かべた。
驚くほど手慣れているのは、まず間違いなく、翡翠に同じことをしているからなのだろう。しかも一度や二度ではなく、日常的にしているに違いない。
そう思うとなんだか悔しくて、思わず意地悪をしてやりたくなった。
「ねぇ、ヨーヘー。翡翠ちゃんにも、こういうことしてるんだね」
少し棘っぽく口にした言葉に、陽平は「ああ」と当たり前のように頷いた。
光海の位置からでは見えないが、きっと平気な顔をして髪に触れているに違いない。
「毎日?」
「ああ。毎朝、縛れって言うからさ」
「私のも、毎日つけて……」
そう言ったらどうする? これは、そんな意地悪な質問のつもりだった。
「ああ、いいぜ。ただし、毎朝うちまで来るンだろぉな」
「え?」
「え、じゃねぇよ。交換条件だろ。毎日ってンならやるけどさ、その代わり毎朝家まで迎えに来いってこと」
それはつまり、毎朝一緒に登校できるということなのだろうか。
陽平と毎朝一瞬に登校できるうえに、一日の初めにリボンを結んでもらう。光海にとっては至れり尽くせりではないか。
「わかった。毎朝、ヨーヘーの家まで迎えに行く」
頷く気配を感じながら、髪にリボンを通される感触を楽しむ。
美容院とはまた違う気持ち良さに頬を染めながら、嬉しさに弛む頬を引き締める努力をしてみるが、このまま徒労に終わりそうな気配だ。
結び終えたのか、背中をぽん、と叩かれ振り返る。
遅れて揺れる髪に、真珠色のリボンが可愛らしく結ってあり、陽平の慣れが伺える。
「ヨーヘー、ありがとう」
「……え? あ、ああ。気にすンなよ! 本当の約束は守れてねぇわけだし……」
誕生日に最高の一日を。その約束を破ってしまったことは、光海の考えている以上に、陽平の後ろめたさになっているようだ。
「あのさ! た、貴仁に……」
「ヨーヘー?」
突然真っ赤になりながら何を言い出すのかと思いきや、陽平は束ねられた光海の髪を軽く持ち上げる。
「あいつに言われたからとかじゃなくて、俺の素直な感想……なんだけどさ」
「ぅ、うん」
「真珠色のリボン、やっぱ似合ってる……ぜ」
恥ずかしさからか、「それだけだ」と踵を返す陽平に、光海は胸の奥底から溢れ出す愛しさを、堪えることなどできはしなかった。
そっと近付き、陽平の肩の辺りを摘むと、くい、と引っ張ってやる。
「なんだよ。もういいだろ? さすがに俺も照れ──」
振り返る陽平の頬に、不意打ちで唇を突き出せば、二人の耳にチュ、という音が届いた。
驚いたように飛び跳ねる陽平に、光海はこの日最高の笑顔を見せる。
恥ずかしさや、珍しい行動に照れているわけではない、掛値なしの笑顔になれたはずだ。
それを証拠に、陽平も安心しきったようにいつもの表情を見せる。

「ありがとう、ヨーヘー。最高の一日だったよ」
一瞬、驚いたように目を丸くする陽平だったが、胸のつかえが取れたとばかりにニカっと笑みを浮かべる。
「その言葉が聞けて、良かった」
「うん」
どちらからともなく寄り添う形で並び立ち、示し合わせることなく同じ速さで歩き出す。
「ねぇ、ヨーヘー」
「ん?」
「来年も、最高の一日が迎えられるかな?」
それは、もう一度こうして二人きりで時間を共有したいと思った光海の願い。
しかし、光海の気持ちを知ってか知らずか、陽平は「さぁな」と答えると、それが当たり前であるかのように光海の手を取った。
「ただ……さ。俺は、そうありたいと思ってる」
「そのためにも、負けちゃだめ……なんだよね」
「負けねぇよ。俺は、翡翠を守るって誓ったンだ。それに、光海のことも」
来年の今日がどうなっているのかは、誰にもわからない。しかし、光海にわかることがひとつだけあった。
(私はきっと、ヨーヘーの隣りにいる)
それは、今までも、そしてこれからも変わらない、当たり前の光景なのだから。
|